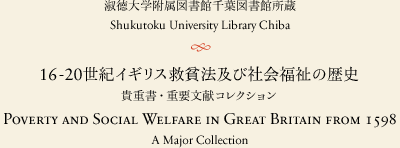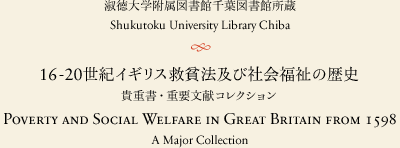|
『16-20世紀・英国救貧法及び社会福祉の歴史 ( 貴重書・重要文献コレクション ) 』 ( 以下、当貴重書・重要文献コレクションと略す ) の概要説明に入る前に、社会福祉研究における当貴重書・重要文献コレクションの価値について簡単に述べたい。
社会福祉という言葉が、資本主義社会の一定の発達段階に応じて使われるようになり、特に社会福祉政策という言葉は、資本主義社会の固有な政策として内部の展開過程で出現したものと把握することは重要なことであう。周知の通り、資本主義経済を世界に先駆けて実現させ、典型的な形で発達してきたのは英国である。そのため英国の社会福祉の歴史は資本主義諸国における社会福祉史の典型として位置づけることができる。
今日の英国を世界における理想的な社会福祉のモデル国、あるいは最高の福祉国家と考えるには、多くの問題が存在するが、英国の社会福祉の歴史研究は、高度の発達段階に達した資本主義社会における社会福祉の隅界を見きわめる意味で、またその段階における社会福祉の真にあるべき姿を求める意味で未だ有益である。
資本主義の展開段階と福祉政策の形成・発展の過程とを対応させながら、両者の意味連関を問う試みは今まで多くの論者によってなされてきた。特に英国の場合、この種の議論で共通しているのが、資本主義の成立期に旧救貧法を、発展期に新救貧法を、没落期前期の古典的帝国主義期に社会事業を、国家独占資本主義期に社会福祉をそれぞれ対応させて考察する試みである。資本主義の展開過程とその時期に対応した諸施策との内在的関連が十分に解明されているわけではないが、それぞれの時代において分水嶺をなした重要な古典的著作、原資料を、当貴重書・重要文献コレクションは有している。
次に、当貴重書・重要文献コレクションの中で特に重視すぺき資料を数冊抽出し、それに関する簡単なコメントを付記することで概要とする。
英国救貧制度の出発点として最も有名な法律は、1601年法であるが、同法は1597年法を単純かつ体系的に整備したものである。当貴重書・重要文献コレクション最古の書『エリザベス救貧法』 ( The Elizabethan Poor Law,1598 ) は、1597年法 ( 39 Elizabethan,c.i〜c.vi,1597−1598 ) のオリジナルであり、英国社会福祉史上最も貴重価値の高い書物と言える。
17世紀の救貧法改革論争は、マッシュウ・ヘイル ( Mathew Hale ) の貧困者に対する雇用の提案から始まり、ダニエル・デフォウ ( Daniel Defoe ) の反対論によって終わる。マッシュウ・ヘイルは、大法官という立場から労働能力のある貧困者の問題に着目し、彼らを組織化することこそ真の慈善であると主張した。彼の著書『貧困者に対する供給に関する講話』 ( A Discourse Touching Provision for the Poor,1683 ) は、彼の死後 ( 7年後 ) に出版されたものであるが彼の見解を知る重要な文献である。
マッシュウ・ヘイルの提案以降活発化した貧困者に対する雇用計画は、ワークハウス設置に向けて発展したが、これらの動きに真正面から反対したのがダニエル・デフォウであり、彼が『施物を与えることは慈善ではない』 ( Giving Alms Nocharity,1704 ) で展開した議論が結局ワークハウス設置法案を葬り去ることになったことは広く知られている。
エリザペス救貧法の下での貧困児童の保護状態を知る上で欠かすことのできない貴重な資料は、ジョナス・ハンウェイ ( Jonas Hanway ) がロンドンの14の教区で1750年から1755年まで実施した調査の報告書である。彼はそこでワークハウスにおける乳幼児が如何に悲惨な状態で収容されているかを赤裸々に描写している。この調査報告はその後整理され、1767年に公にされた『ロンドン貧困者内の幼児死亡率』 ( lnfant Mortality Amongest the London Poor,1767 ) で結実している。
英国において産業革命が進展し、第2次エンクロージャーが展開される中で、救貧行政が一時的ではあるがそれまでとは異なる方向で大きな変遷を見せる。その変遷は、1782年法 ( An Act for better Relief and Employment of the Poor, 22 George III, c. 83 ) ( 通称、ギルバート法 ) と、同法を基礎に形成されたスピーナムランド制度 ( Speenhamland System ) を契機として起こったと考えれる。特にギルバート法は、リッチフィールド選出の代議士トーマス・ギルバート ( Thomas Gilbert ) の努力によって立法化され、『人道主義化』を法的に確認し、具体的には労働能力のある貧困者に対して居宅保護を認めた点に蓄いて意義深い。そのため1775年にトーマス・ギルバートが議会提出用に作成したギルバート法案 ( Gilbert's Bil1,1775 ) は、貴重な資料価値を有していると言える。
1795年サミュエル・ホイットブレッド ( Samuel Whitbread ) が議会に提出した最低賃金法案が、トーマス・ロバート・マルサス ( Thomas Robert Malthus ) の影響を受けた自由主義の信奉者ウイリアム・ピット ( William Pitt ) によって痛烈に批判され葬り去られたことはよく知られている。しかしそのホイットブレッド宛にマルサスが送った手紙 ( Malthus on Whitbread's Bill ) について知る者は少ない。貧困者の状態の改善について根本的に悲観的であったマルサスは、その手紙にホイットブレッドの法案が誤った認識の上に基礎づけられていることを記している。
トーマス・チャーマズ ( Thomas Chalmers ) は、英国社会事業の理論 ( 方法論 ) を形成した先駆者として、また慈善組織協会 ( Charity Organisation Society ) に大きな影響を与えた人物として著名であるが、彼の功績は、グラスゴー市での宗教活動を通じて理論を形成し、それを同市で実践したことである。当貴重書・重要文献コレクションに収められている数冊のチャーマズ関連文献 ( Hospital for the Poor and Report on the Management of the Poor in Glasgow, 1818 / The Christian and Civic Economy of Large Towns, 1821-1826 / Pauperism in Glasgow, 1823 ) は、これまで十分探究されていない彼の業績を解明する上で第一次的資料である。
1601年以降伝統をもつ救貧法が、1832年に組織された救貧法改正案作成のための王立委員会によって大幅に改正されたことは、英国社会福祉史上欠くことのできない重要な出来事である。同委貝会に提出された報告書 ( Report from His Majesty's Commissioners for Inquiring into the Administration and Practical Operation of the Poor Laws ) は、ナソー・シーニァー ( Nassau William Senior ) とエドウィン・チャドウィック ( Edwin Chadwick ) によって起草されたが、新救貧法 ( Poor Law Amendment Act ) の成立に大きな影響を与えたものである。またエドウィン・チャドウィックが1842年に上院に提出した『英国労働者の衛生状態に関する報告』 ( Local Reports on the Sanitary Condition of the Labouring Population of England, 1842 ) は、1848年に成立した公衆衛生法に貢献した書として今日でも高く評価されている。
1854年に出版されたジョージ・ニコルズ ( George Nicholls ) の『英国救貧法史』 ( 全2巻 ) ( A History of the English Poor Law, 2 vo1. ) は、英国救貧法史のバイブル的文献で日本の社会福祉研究者が英国の救貧法の歴史を分析する際に最も活用した書である。
世界最初のセツルメント・ハウスにその名を残したアーノルド・トインビー ( Arnold Toynbee ) が、ヘンリー・ジョージ ( Henry George ) が著した『進歩と貧困』 ( Progress and Poverty ) を批評した2回の講演 ( Amold Toynbee Answers Henry George ) は、初期のフェビァン協会 ( Fabian Society ) の執行委員やその後の社会改良主義者に大きな影響を与えたものと伝えられている。
19世紀末から20世紀にかけて行われたチャールズ・ブーズ ( Charles Booth ) のロンドン調査と、ベンジャミン・シーボーム・ラウントリー ( Benjamin Seebohm Rowntree ) のヨーク調査が、英国における貧困問題の深刻さを一般大衆に示したことは周知の事実である。
ブーズは自ら資金を調達し、1886年から1888年にかけてロンドンの貧困調査を行い、そ切結果を1892年から1897年にかけて『ロンドン貧困者の生活と労働』 ( Life and Labour of the London Poor ) という10巻の報告書として発表した。またそれを加筆・修正し、整理し直したものが、1902年から1904年までに『ロンドン市民の生活と労働』 ( Life and Labour of the People in London ) という全17巻の報告書として出版されている。
ラウントリーは、ヨーク市で1899年貧困原因の調査を行い、その結果を1901年『貧困 − 都会生活の研究』 ( Poverty. A Study of Town Life ) という報告書で発表した。また彼が1936年に実施した第2次調査は、『貧困と進歩』 ( Poverty and Progress ) というタイトルで1941年に刊行されたが、当貴重書・重要文献コレクションが有する同書は、筆者であるラウントリー直筆の署名が記されておりその価値を高めている。
『救貧法並びに貧困救済に関する王立委員会』 ( Royal Commission on the Poor Laws and Relief of Distress ) に1909年提出された2つの報告書『救貧法並びに貧困救済に関する王立委員会の報告書』 ( Report of the Royal Commission on the poor Laws and Relief of Distress ) と『分離報告書』 ( Separate Report〉 ( 通常、この2つの報告書の前者を『多数派報告』 ( Majority Report ) 、後者を『少数派報告』 ( Minority Report ) と呼んでいる。 ) は、英国社会福祉政策史上重要な意味をもつ公文書である。特にシドニー・ウェッブ ( Sidney Webb ) とビアトリス・ウェッブ ( Beatrice Webb ) によって作成された『少数派報告』は、救貧法の撤廃 ( The Break-up of the Poor Law ) と「労働市場の公的組織化」 ( The Public Organisation of the Labour Market ) を提唱し、第2次世界大戦後発展する福祉国家理念の先導的文書と考えられている。
同王立委員会においてビアトリス・ウェッブが中心となって行った救貧法の歴史に関する実証的歴史研究の成果は、ウェッブ夫妻の共著『英国救貧法史』 ( English Poor Law History: PartI, PartII, 1927, 1929 ) にまとめられている。また『多数派報告』の起草に貢献したCOSの理論的指導者ヘレン・ボーザンケト ( Helen Bosanquet ) が執筆した『1909年の救貧法報告』 ( The Poor Law Report of 1909, 1909 ) は、『多数派報告』の主張を内在的に分析する上で有益な資料である。
( 淑徳大学 金子光一 )
|