授業・カリキュラム
管理栄養士+αの知識を得られる本学独自の授業内容
医療チームや地域社会に貢献できる人材を育成します
医療現場では、管理栄養士は医師や看護師らと共にチームの一員として個々の患者さんに合わせた栄養管理や食事管理を行います。福祉施設や地域においても、「食」の観点から健康づくりの活動を行える栄養の専門家を育成します。
「看護」と「福祉」の知識とマインドを身につける
栄養学科では、栄養学分野の他にも、看護や福祉など、他学部・他学科と学ぶ授業が設けられています。栄養学についての理解を深めるだけでなく、「看護」や「福祉」の知識・理解をもった栄養の専門家を育成します。

多様なボランティア活動
本学の建学の精神である「利他共生」には人々に"感謝"の気持ちを持つという思想があります。地域住民の方々が主催する運動会、認知症カフェ、子ども食堂やゴールドリボンウォーキング(小児がんの子ども達を応援する活動)などの様々なボランティアの機会があり、地域住民や社会の方々との触れ合いを通じて【共に生き、共に生かし合う】という価値観を身につけ、人間としても成長する機会に溢れています。
はじめての学生でも安心して参加できるように「ボランティア講座」があるのも本学ならではの特徴です。
はじめての学生でも安心して参加できるように「ボランティア講座」があるのも本学ならではの特徴です。

充実した国家試験対策プログラム
入学前からの「学力強化対策」をはじめ、低学年からの「学修支援」、「国家試験対策」などのサポート体制が充実しています。国家試験を受けるまでの心構えや年間スケジュールのガイダンス、メンタルサポートなど、個人の理解度に応じてきめ細やかに学生を支援しています。教員や外部講師による対策講座や自分の不得意を客観的に把握するための模擬試験も実施します。

栄養学科の実学|女子柔道部を栄養指導
選手のサポートを通じて栄養指導を実践
卒業研究のテーマの一つに、「スポーツと栄養」を学ぶ実践の場として、栄養学科の学生と女子柔道部の選手がペアになり、食事記録をフィードバックする方法で栄養指導を行っています。選手の栄養状態を評価し、一人ひとりに適切なアドバイスを行う貴重な機会です。今後も継続的に指導を行い、選手のコンディション向上に貢献していきます。
卒業生の声|学びを活かす
地域の人々の健康維持・増進を支える
行政栄養士になりたい
病院や学校などで100食提供することを想定した大量調理を10人のグループで取り組みました。献立作成から栄養管理、材料発注、調理などに給食に関わる全行程に携わるので、役割分担やチームワークが欠かせません。私は班長だったのでメンバーを信頼し、任せることを心掛けました。給食経営管理の知識に加え、メンバーと協力することの大切さに気づくことができた授業です。皆川 遥加 さん(山形県立新庄北高等学校 出身)
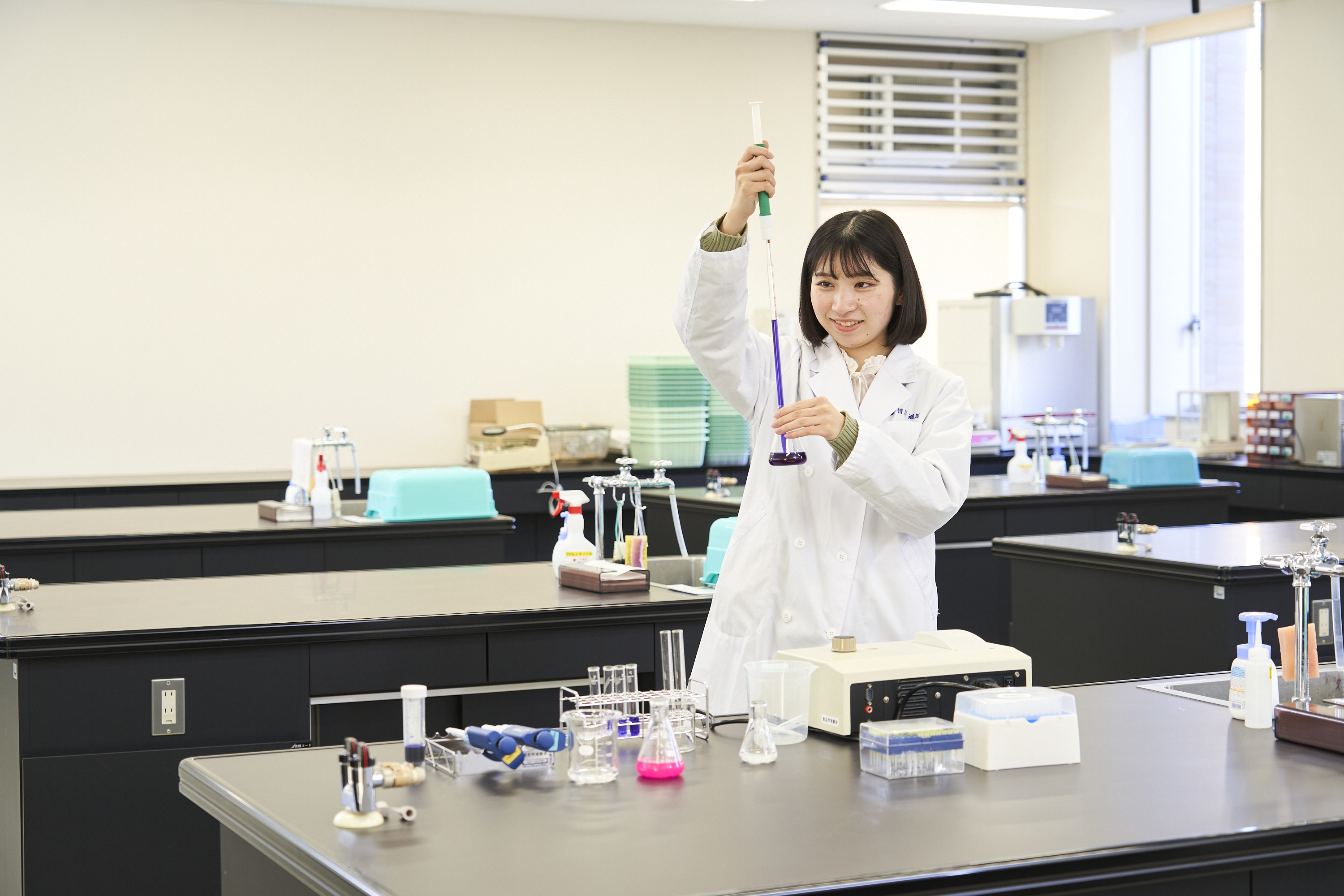
4年間の学び
全学共通の基礎教育科目 S-BASIC
専門教育科目
基礎系科目・実験実習で理解を深める

調理学実習Ⅰ
調理の実践を通して食品の持つ特性を理解する
食品の調理特性や調理加工による物性の変化を理解し、調理技術の基礎を修得します。
| カリキュラム |
| 専門教育科目 |
●健康管理論
●社会福祉学概論
●生化学
●解剖生理学Ⅰ
●解剖生理学Ⅱ
●解剖生理学実験
●微生物学
●社会福祉学概論
●生化学
●解剖生理学Ⅰ
●解剖生理学Ⅱ
●解剖生理学実験
●微生物学
●微生物学実験
●食品化学Ⅰ
●食品化学Ⅱ
●食品化学実験Ⅰ
●食品化学実験Ⅱ
●調理学
●調理学実習Ⅰ
●食品化学Ⅰ
●食品化学Ⅱ
●食品化学実験Ⅰ
●食品化学実験Ⅱ
●調理学
●調理学実習Ⅰ
●調理学実習Ⅱ
●基礎栄養学
●基礎栄養学実験
●応用栄養学Ⅰ
●心理学概論
●カウンセリング論
●フードスペシャリスト論
●基礎栄養学
●基礎栄養学実験
●応用栄養学Ⅰ
●心理学概論
●カウンセリング論
●フードスペシャリスト論
教職科目
|
●教職概論
●教育心理学
●発達心理学
基礎教育科目 |
○初年次セミナー(学習の目的と技術)
○利他共生
○情報リテラシー
○データリテラシー
○利他共生
○情報リテラシー
○データリテラシー
○コミュニケーション英語Ⅰ(基礎)
○コミュニケーション英語Ⅱ(応用)
○表現技法Ⅰ(読解・分析)
○表現技法Ⅱ(作文・論文)
○コミュニケーション英語Ⅱ(応用)
○表現技法Ⅰ(読解・分析)
○表現技法Ⅱ(作文・論文)
○自己管理と社会規範
○チームワークとリーダーシップ
○チームワークとリーダーシップ
基礎教育科目(1~4年次) |
○人間心理と人間行動
○現代家族と育児介護
○現代家族と育児介護
○健康管理と身体活動
○スポーツと運動科学
○スポーツと運動科学
○日本社会と歴史文化
知識の修得から実践へ

栄養教育論実習
医療・福祉・学校等の現場で活きる
実践的な栄養教育の形を学ぶ
実践的な栄養教育の形を学ぶ
栄養教育に必要な知識と技術の向上をめざし、栄養計画書や教材を作成し、実践的な教育スキルを身につけます。
| カリキュラム |
| 専門教育科目 |
●公衆衛生学
●生化学実験
●栄養生化学実験
●病理病態学Ⅰ
●食品衛生学
●食品衛生学実験
●調理科学実験
●生化学実験
●栄養生化学実験
●病理病態学Ⅰ
●食品衛生学
●食品衛生学実験
●調理科学実験
●応用栄養学Ⅱ
●応用栄養学実習
●栄養教育論Ⅰ
●栄養教育論Ⅱ
●栄養教育論実習Ⅰ
●臨床栄養学Ⅰ
●臨床栄養学Ⅱ
●応用栄養学実習
●栄養教育論Ⅰ
●栄養教育論Ⅱ
●栄養教育論実習Ⅰ
●臨床栄養学Ⅰ
●臨床栄養学Ⅱ
●臨床栄養学実習Ⅰ
●公衆栄養学Ⅰ
●給食経営管理論Ⅰ
●給食経営管理論Ⅱ
●食品評価論
●食品流通論
●公衆栄養学Ⅰ
●給食経営管理論Ⅰ
●給食経営管理論Ⅱ
●食品評価論
●食品流通論
教職科目 |
●教育課程論
●教育の方法と技術(情報通信技術の活用を含む。)
●総合的な学習の時間と特別活動の指導法
基礎教育科目 |
○コミュニケーション英語Ⅲ(実践)
○コミュニケーション英語Ⅳ(実践)
○コミュニケーション英語Ⅳ(実践)
○表現技法Ⅲ(発表・討論)
○表現技法Ⅳ(企画・立案)
○表現技法Ⅳ(企画・立案)
○統計分析法
○社会的・職業的自立Ⅰ
○社会的・職業的自立Ⅱ
○社会的・職業的自立Ⅰ
○社会的・職業的自立Ⅱ
基礎教育科目(1~4年次) |
○生命科学と物理化学
○情報社会とデータサイエンス
○情報社会とデータサイエンス
○法律社会と法律問題
○福祉政策と福祉制度
○福祉政策と福祉制度
○日本国家と政治行政
○経済構造と経済政策
○経済構造と経済政策
臨地実習で現場を知る

給食経営管理論実習
一連の給食システムを
体系的に学べる学内実習
体系的に学べる学内実習
栄養・食事計画として献立を作成し、100食以上の調理を実施。食材管理、品質管理、衛生管理、設備管理などを学びます。
| カリキュラム |
| 専門教育科目 |
●保健医療統計学
●疫学
●分子栄養学
●病理病態学Ⅱ
●応用栄養学Ⅲ
●栄養教育論Ⅲ
●栄養教育論実習Ⅱ
●疫学
●分子栄養学
●病理病態学Ⅱ
●応用栄養学Ⅲ
●栄養教育論Ⅲ
●栄養教育論実習Ⅱ
●臨床栄養学Ⅲ
●臨床栄養学Ⅳ
●臨床栄養学実習Ⅱ
●公衆栄養学Ⅱ
●公衆栄養学実習
●給食経営管理論実習
●総合演習Ⅰ
●総合演習Ⅱ
●臨床栄養学Ⅳ
●臨床栄養学実習Ⅱ
●公衆栄養学Ⅱ
●公衆栄養学実習
●給食経営管理論実習
●総合演習Ⅰ
●総合演習Ⅱ
●公衆栄養学臨地実習★
●給食経営管理論臨地実習★
●給食管理臨地実習
●臨床栄養学臨地実習
●フードコーディネート論
●専門職ネットワーク演習
★いずれか選択必修
●給食経営管理論臨地実習★
●給食管理臨地実習
●臨床栄養学臨地実習
●フードコーディネート論
●専門職ネットワーク演習
★いずれか選択必修
教職科目 |
●道徳の指導法
●生徒指導の理論と方法
●生徒指導の理論と方法
●教育相談の理論と方法
●学校栄養教育法
●学校栄養教育法
●学校栄養指導論
基礎教育科目 |
○問題解決法
○表現技法Ⅴ(プレゼンテーション)
基礎教育科目(1~4年次) |
○経済構造と経済政策
○現代医療と生命倫理
○現代医療と生命倫理
○国際社会と国際問題
○世界宗教と民族問題
○世界宗教と民族問題
○世界動向と国際貢献
○国際平和と安全保障
○国際平和と安全保障
卒業研究を通して
栄養学の理解を深める
栄養学の理解を深める

卒業研究テーマ
- 千葉市在住の後期高齢者の栄養状態について国民健康・栄養調査との比較
- 2型糖尿病における慢性炎症とインスリン抵抗性の機序について
- 難消化性デキストリン含有茶飲料の摂取による食後血糖値変動についての試行
- COⅥD-19感染症拡大防止のための地域活動休止が高齢者の身体機能や栄養状態に及ぼす影響
- 女子柔道部選手の体重管理における栄養介入
- 辛味と塩味の認知閾値、嗜好性および食物摂取状況の関連に関する研究
- 診療所における食塩摂取量の評価と減塩指導の効率化に関する研究
- 難消化性多糖類がマルトース分解酵素活性に及ぼす影響の検討
- 地域高齢者等の健康支援を目的とした千葉県内配食サービスの実態に関する文献調査
- 食事バランスガイドの認知と食習慣の関連性
※テーマは一例となります
| カリキュラム |
| 専門教育科目 |
●管理栄養士演習
●卒業研究Ⅰ
●卒業研究Ⅱ
●卒業研究Ⅱ
●有機化学
教職科目 |
●教育原理
●特別支援教育の理解と方法
●特別支援教育の理解と方法
●教育行政学
●日本国憲法
●日本国憲法
●栄養教育実習事前・事後指導
●栄養教育実習
●教職実践演習(栄養教諭)
●栄養教育実習
●教職実践演習(栄養教諭)
基礎教育科目 |
○創造思考法
○地域活動と社会貢献
○他者理解と信頼関係
基礎教育科目(1~4年次) |
○国際関係と日本外交
○地球環境と環境対策
カリキュラムの詳細は、栄養学科カリキュラム表をご覧ください。※前期、後期などの開講時期は変更することがあります。
正しい 開講学期は毎学期S-Naviの時間割を確認してください。
学びの集大成 卒業研究
卒業研究は4年次に取り組む研究で、大学教育ならではの単位として認定されています。3年生までに学んできた分野の中から自分が興味をもつものを選択し、研究や調査を重ねてきた成果を発表します。卒業研究は一人で一つのテーマに取り組む場合、そして数名で同じテーマに取り組む共同作業の場合もあります。
演題(一部抜粋)
- 地域連携に関わる子ども食堂での活動~年間メニュー計画とポイント~
- 小学校の食育活動推進のための千葉県特産物を生かしたレシピ開発
- 子どもの貧困対策の推進に関する都道府県計画の策定状況~栄養・食生活面に着目して~
- 辛味と塩味の認知閾値、嗜好性および食物摂取状況の関連に関する研究
- うつ病治療におけるプレバイオティクス・プロバイオティクスを利用したア
プローチ~脳腸相関の視点から~ - ゴボウ添加が糖質分解酵素活性に及ぼす効果:食塩、調味料存在下および加
熱による影響の検討 - 防カビ剤の現状及び輸入果物について
- フレイル高齢者の食料品アクセス特徴の明確化
- 白旗台地域の在宅高齢者の栄養状態と食習慣について‐第2 報‐
- 世界の食塩摂取基準と減塩対策
- 大学女子柔道部選手の栄養課題に対する個別指導


