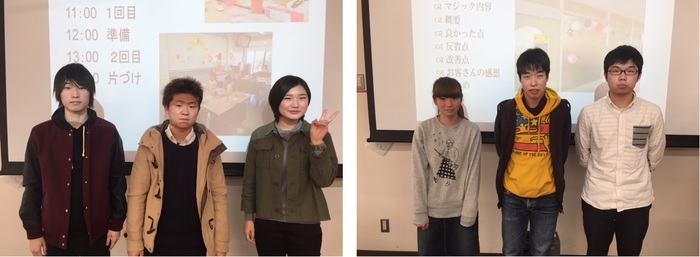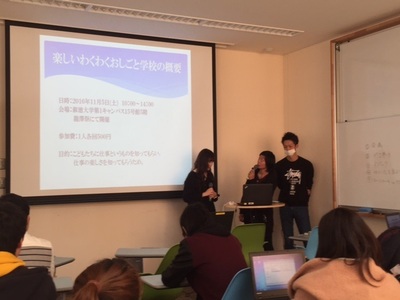問題から逃げるのは基本的に良くない。
問題の状態が変わってなければストレスの原因は変わらないから。
――思ったよりここの心理の学生さん心理に情熱を注いでいる人が少ない気がするので僕は結構びっくりしてる…面白いなって思うんですけどね!
――でも確かにみんな文系から入ってきちゃったりする子が多い。
――そうなんだよね。
うんうん。
――だからいざ講義を受けてみてギャップというか。
――まあ確かに理系的な話はある。
――驚いちゃってる部分があるので、そこからみんな躓いちゃってるかなっていうのはあります。
うん。そうだよね。やっぱり分析的なところがあるからね。客観的分析とかね。
――あと生物の話も多いじゃないですか。
――ああ~~。
――脳の構造とかそういうのって文系の人からすると「別にな」って部分があるんじゃないですかね。
――びっくりしました!脳のことまでやるんだって。神経のこととか。
僕も生化学者と一緒に仕事したことあるから。ネズミの脳を破壊したり、薬物注入したりして、迷路を走らせて成績はどうなるかっていう…
――うわ、結構…
一同:…ははは
――怖い研究してるんですね。
――いや~~。
脳に薬物を注入するとね、成績が上がったりすることがある。
――え、薬物をやると成績が上がる?
短い時間だけどね。
――あ~~。
またすぐにダメになる、ふふ。
――あはは
心理学そういうふうに理系の人とも一緒にできるみたいなところが僕は面白いなって思うんだけどね。でも確かにね、あるところでダメだって思っちゃうと結構苦痛なところが多いかもしれないよね。
――うん。
脳の仕組みねえ…。神経心理とか面白いと思うんだけど。
――入ったときびっくりしたよね。
――ギャップありましたね。
――これをやるのかって。最終的には面白くなったんですけど。
僕はそういうのをやるもんだって思って入ったよ。
――やっぱり違うんですね。最初の入りが。
うん。僕が学生の頃は臨床心理ほとんどなかったから。ないっていうか心理学の主流から完全に外れたものだったので、それであんまり言わなかったよね。あんまり言っちゃいけない雰囲気が漂ってたし。
――やっぱり理系の方が多かったんですかね。当時。
う~ん。
――両方好きな人が入るんですかね。
いや、今考えると、心理学自体が自然科学になろうと無理していたところはあると思うんだよね。実験実習は白衣着なきゃいけない時代だったので。それってほとんど医者とか理系の研究者の真似だったと思うんだよね。そういう自然科学もどきみたいなのがあって、それで昔は文系的なものを低く見ていたんじゃないかな。でも実際には、そういう分野もあれば、そうじゃない分野もあるからこそ心理学は広く問題を扱えるんじゃないかなって思うんだけどね。
――やっぱり今の時代って、先生が学生だった時と違ってすごく心理に対して社会が寛容になっているというか…。十何人に一人がパーソナリティー障害なる可能性がある状況じゃないですか。先生が学生のときはそういう患者さんの位置づけって今と違いますか?
発達障害とかいたんだろうけどまだ命名はされてなかったので。命名がされていないということはそれは気づかれないないということだから。精神障害の中でもかなりコアな部分だけが臨床の対象になってたということはあるんじゃないかな。さっき言ったように心理学自体が自然科学的なものを指向するのが強かったと思うんだよね、当時はまだ。僕が学生のときは基本的に卒業論文は実験じゃなきゃいけなかったから。質問紙だとちょっとなあ…という感じ。
――今はだいたい質問紙ですもんね。
うん。当然インタビューとかではダメという時代だったので…。そういう意味で変わってきたと思うし。今、心理学は大きく二つに分かれているところがあって、神経心理学とか進化心理学とかますます自然科学的な心理学、一方で臨床っていうので大きく分かれているかな。大学によっては臨床がないところがあるし、外国なんかだとね。これからまた変わっていくでしょうけれども。
――確かに母親が子どもの時障害者の方に対する見方とかが全然違ったと言っていたので、今はすごいと思います。
――昔は精神障害というだけで隔離とかされていたじゃないですか。今はカウンセリングで治していきましょうという感じじゃないですか。昔はそのまま隔離されてしまう…。いつから寛容になってきたんですかね。
寛容さだけではなくて精神医学の薬物の治療が進んだっていうのが一番大きいと思うんだ。統合失調症はかなり長期に渡ったりとか治らないっていうのが強かったけれど、最近では適切な薬物が投与されれば状態が良くなったりとか。それを続けることによって社会復帰とか、通院で済む場合も増えてきたんで。それはまあ気分障害、鬱とかにも言えるので。さっきの理系と文系っていう意味では、理系的な薬物の治療が進んできたっていうこと、あとは心理療法でも認知行動療法とかでてきたっていうのが組み合わさってきて。そして自然科学的な薬物療法が進んだってことが、社会復帰とか社会的なことも進み、両者は切り離せないところがあるんじゃないかな。今こうやって録音して細かいやり取りを起こすことができるけれども、以前はできなかった。同じように、技術が変わっていくということは、同時に社会や心理学も変わっていくところがあるので。たぶんこれからも技術が進歩してくと、社会の在り方も変わっていくと思う。どういう人を障がい者と呼ぶかみたいなのもね、変わっていくんじゃないかな。
――うーん。なるほど。
――質問なんですけど、ストレス解消とかされてますか?
僕はストレスの研究もしていたことがあるんだけど。ストレスは、原因があって、反応が出るっていうので。ストレスの発散っていうのは、ストレスの理論には無くて。
――ああ。
カラオケに行くっていうああいうのはあんまりよくないとされているんです。
――そうなんですか(笑)
――知らなかった(笑)
問題からそれてしまうので。
――なるほど。
ストレスの原因を消さないと。
――ああ~。
――根本的な解決にはならないってことですか。
そうそう。
――みんな行ってますよね(笑)
――間違っているんですね(笑)
それによって、同じような不満や悩みを持っている仲間同士で互いに俺も大変だよっていう形で共感しあってストレスが減るっていうのある。サポートしあってっていうのはあるけれど。問題から逃げるのは基本的に良くない。問題の状態が変わらなければストレスの原因は変わらないから。
――なるほど。
――じゃあ先生は原因と向き合う感じですか?
んー、いや。逃げるときは逃げるけどね(笑)例えば日本の会社は終身雇用なので、今言ったような意味では、我慢して上司が変わるのを待つとかそういうやり方があるんだけど。アメリカの教科書を読むとそういう時は転職しなさいって書いてあるんだよね。転職すればストレッサーが無くなるから。
――なるほど。
だから社会によって違うんだよね。アメリカの研究がそのまま日本では役立たないということがあるので。僕は、ストレスの原因は何か、これは対処できるのか考えて、対処できるとしたらどう対処すればいいかっていうことを考える。そういう意味ではストレス発散はしない。
――びっくりしました。
カラオケに行っても解決…
――しないですね(笑)カラオケ終わった後に考えちゃいますもんね。
うん(笑)それだけだとあんまり意味がないかもしれないね。
――一時的なものですね。
――学生の皆さんにも教えてあげたい(笑)
うん(笑)
――カラオケ行っても意味ないよって(笑)
――ブログに書かなきゃ!(笑)
そう、だからアメリカと日本では違うように、その社会の中で対処法って違うと思うんだよね。バイトだったらやめれば済むかもしれないよね。それは一つのやり方だと思うんだよね。大学でも嫌だったらやめるっていうのも一つのやり方かもしれないし。やめないとしたら次どうしていくかっていうのをね。先生とうまくいかないんだったら、先生とうまくいくにはどうしていくのかって考えるのがいいよね。心理学を学ぶとこういうことがわかる(笑)対処法を考えなきゃいけない。よく考えるとスポーツ選手なんかはそうやって解決しているよね。プレッシャーとか多い時にどうするか。逃げるってことはしない。
――逃げまっくてるな、そう考えると。
――あはは(笑)
ふふふ(笑)逃げきれればもう一つの手かなって思うんだけど。
――うん、でもまた選択肢として使ってしまう。
達成したかったことができなくなってしまうからね。逃げ続けるとね。だから目先の逃げを重視するのか。
――ずっと逃げ続けたツケがいつ回ってくるのかってびくびくしてます(笑)
ふふふ(笑)
――淑徳の学生にむけて何かメッセージをよろしくお願いします。
まず心理学は純粋に面白い分野じゃないかなあと。特に人間に興味がある人にとってはかなり面白い分野なんじゃないかなって思います。それにまだわかってないことも多いので、やっていくと、そういうことを明らかにしていく楽しみ方もできるんじゃないかな。心理的なことで悩んでいる人も、考えるきっかけみたいなものは大学に来てわかるんじゃないかな。結構自分で悩んでるとか、そういうので心理学を学びたいって人も多いよね。仕組みをわかったりとか。ああこんなものかって気が楽になったり。
――そうですよね、仕組みがわかったら、案外単純なんだって。それがわかったとき怖がっても仕方なかったのかなって。心理学を学んで楽になった気がします。
うんうん。
――はい、インタビューありがとうございました!先生がインタビューのトップバッターだったんですが大橋先生のお話しとても勉強になりました。ありがとうございました。
――ありがとうございました!












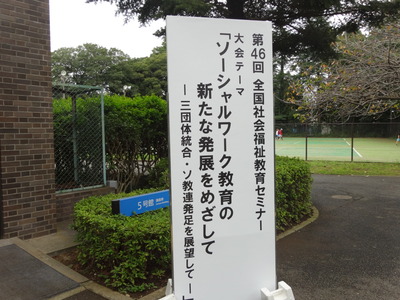



 当日の様子
当日の様子