univ_news_center
地域共生センター
2024.08.01
淑徳大学 公開講座【総合福祉研究科 ・地域共生センター共催】 地域共生社会づくり ~移動支援の視点から考える~を実施しました
この度、元厚生労働省事務次官 蒲原基道先生をお招きし、地域包括ケア、地域共生社会づくりの「地域づくり」の重要性と地域づくりについて「移動支援」を例に、自分らしく暮らすための「移動」の重要性や、買い物などの暮らしの継続を支える移動支援の仕組みについてご講演いただきました。約40名の学生・院生・教職員や地域の方々がご参加くださいました。
| 開催日 | 2024年7月26日(金) |
| 時 間 | 13:00~14:30 |
| 場 所 | 淑徳大学 千葉キャンパス 淑水記念館2階 多目的室 |
| 講演タイトル | 地域共生社会づくり ~移動支援の視点から考える~ |
| 講 師 | 淑徳大学 客員教授 元厚生労働省事務次官 蒲原 基道 先生 |
| 実施主体(共催) | 淑徳大学 総合福祉研究科・淑徳大学 地域共生センター |
●高齢者を中心に「買い物」「通院」「交流の場への参加」など、移動弱者の課題が多い現代社会、さまざまな地域での対策を紹介しながら解説いただきました
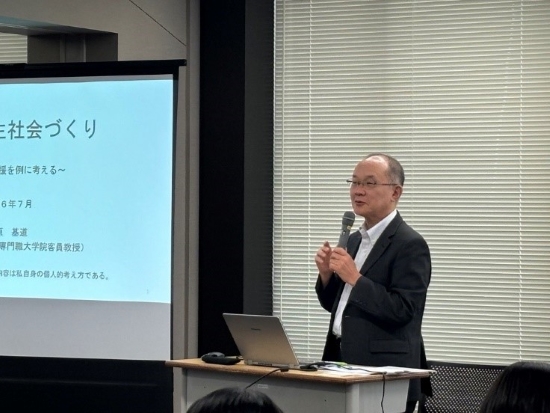

●受講者からもたくさんの感想や質問が寄せられました
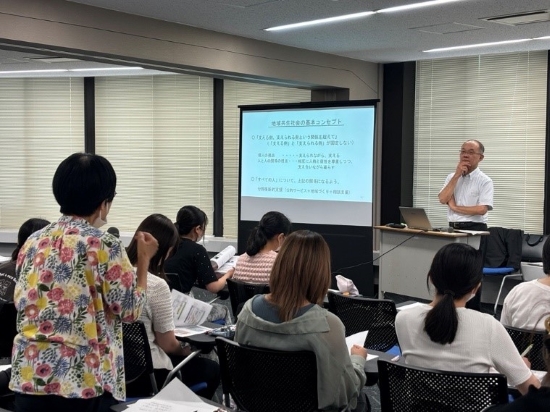

●受講者からの感想(抜粋)
- 移動支援について知らないことが多くあったので今回のお話を機に学ぶことが出来てよかった。移動支援を行う時に、利用する側は高齢者や障害者の方だというイメージはあったけれど、実施する側にボランティアとして高齢者の方が参加することでその人自身の予防になると聞いてその視点はなかったので勉強になった。 どうしても支援と考えると利用する側として捉えてしまうけれど一緒に作っていくことも支援に繋がると考えるきっかけになったと思う。移動支援を行う時の申請の段階で諦めてしまう団体もあるということだったのでもう少し申請の仕方やはじめ方を広める活動が必要だと思った。
- 移動支援における運転手といったその地域の元気高齢者が行っているように、支援する側とされる側で分けず、あらゆる立場の人が役割を持つことで、自分が必要とされているという感覚を持つことが出来るため、そうした早い段階からの対応が重症化しない介護予防の取り組みに繋がっていくことを知り、地域で活躍するといった軸をつくることがどれほど大切なのか分かった。また、スローレジのようにその人の出来ないことをそのままにするのではなく仕組みを変えて、認知症の人でも出来るようにするといった出来ることをそのまま活かすといった支援はとても素敵だなと感じた。
- 私は相談援助の授業で認知症カフェの提案書を立案するというグループワークを行っているが、協力者や企画者として学生ボランティアや地域住民、当事者の協力・支援を得るという考えしか出てこなかった。 今回の講義で取り上げられていた、タリーズコーヒーが認知症カフェの場所提供をしているというお話を受け、企業と協力するという新たな視点を見つけることが出来た。また、居場所・憩いの場・行きつけの場所という点では認知症に限らず、視野を広げ引きこもりの方や母子、児童などの多方向の視点で捉え支援していく、つまり分野横断的な関わりが必要だということを学んだ。
淑徳大学地域共生センターでは、今後も本学の専門的教育・研究や各キャンパスで取り組まれている地域活動・ボランティア活動との相乗効果を働かせながら、知的資源を地域社会へと開放する公開講座を展開してまいります。
淑徳大学地域共生センター